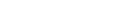意外と知られていない売却後の歯科医師と売却後の歯科医院運営
真に大切なのはクロージング後の医院と売主
歯科医院のM&Aにおいて、一般的な仲介会社は、クロージング(取引成立)をゴールとしています。
多くの仲介会社は、買手が売手に資金を支払い、経営権が移行するまでがサービス範囲であるため、M&A後の医院運営や売却後のオーナーの生活について深く関わりません。
つまり、本当に大切なM&A後の院長や医院については、知らないという仲介会社が多く存在します。
しかし、弊社では売却後の歯科医師との関係も重視しています。
なぜなら、本当に弊社の支援したM&Aにご満足いただけているかどうかは、その後、数年の時を経てみないと分からないからです。
歯科診療に例えるならば、セットした瞬間は、審美性がとても良い補綴物があったとします。
セット当日、患者さんはその見た目に満足されたとしても、中長期的に見て、咬合の不調を感じたり、何度も破損したりするなどのケースも考えられます。
そういったケースでは、患者さんは真に満足されているでしょうか?
M&Aも同様に、中長期的に売主の歯科医師とお付き合いさせていただき、先生と医院のその後を未届けなければ、真に良いサービスを提供できたかどうかは分かりません。
弊社では、医院を売却した多くの院長とお付き合いを続け、ライフスタイルや心情の変化、M&Aをして良かった点や改善すべき点について直接お聞きしてまいりました。
売手歯科医師と医院の売却後が大事だと考えて弊社が行動しているからこそ得られる、M&A後の歯科医師や従業員の情報は、一般的な仲介会社が持っていない知見であると考えています。

過去の歯科医院の譲渡はどういったものだったのか
10年前までは、歯科医院の出口戦略の選択肢が少なかった
10年前の歯科医院の売却(譲渡)は、現在と比べて少数であり、特に利益が1億円以上出ているような大型医院の売却はほとんど見られませんでした。
また、当時の売却は引退を目前に控えた院長が、臨床も含めて完全引退するケースが多かったと言えます。
60代後半から70代の院長が若手の歯科医師に「居抜き」で医院を売却し、自身は引退して余生を楽しむといった流れが一般的で、売却後も新たな環境で働き続けるという選択肢はほとんどありませんでした。
リタイア後の生活の多様化が進んでいなかったこと、40代や50代の若手歯科医師の売却事例がほとんどなかったことが背景にあり、売却後に新しい働き方を模索する概念が希薄だったためと考えられます。
歯科医院M&Aの最新トレンド
ここ数年、歯科医院の売却(譲渡)後の働き方には大きな変化が見られます。
最近では40代や50代といった若い世代の歯科医師による売却が増加しており、売却後も新しい環境で働き続けるというスタイルが広まっています。
40代で売却をしても経済的にはリタイアが可能な場合が多いものの、実際には早期リタイアを選ばないケースも少なくありません。
完全に引退して週7日家にいるライフスタイルは必ずしも好まれず、新たな環境の下で働くことを求める傾向が強まっています。
このように、若い歯科医師が経済的自由を得た後も自らのスキルを活かして働き続けるというスタイルが、最近見られる傾向です。
具体的な事例について
クリニックの状況について
具体的な事例として、西日本にある50代前半の院長が経営するクリニックをご紹介します。
売却前、本事例のクリニックは5院以上を構え、従業員数も大規模体制の100名以上、年間売上は10億~15億円に達していました。
利益も数億円単位と安定した収益を上げており、非常に健全な経営状況であったと言えるでしょう。
売却者の状況とクリニックの売却(譲渡)を検討した経緯
自ら先頭に立って意思決定し、医院の規模を拡大してきた院長は、健康に不安はなく、経営に意欲的で、さらなるクリニック拡大を考えていました。
一方で、後継者が不在だったこともあり、院長は自身が経営を続けられなくなった場合の従業員やその家族の生活への影響を強く懸念していました。
従業員の生活を守りながら経営を続けていくには、経営パートナーの存在が必要と感じたことが売却を検討した経緯です。
売却までの流れ
転機となったのが、投資ファンドとの出会いです。
ファンドの資金力と経営サポートによりクリニックを成長させられる点と、院長が経営を続けられなくなっても医院が法人として存続できる点に魅力を感じ、売却を決意。
経営パートナーとしての役割を担える買手を選んだことで、従業員の生活保障を確保しながら、クリニック拡大に尽力できる環境を実現できました。
ファンドについて
投資ファンドというと、経営が傾いている企業を安く買収し、短期的に売却して利益を狙ういわゆる「ハゲタカファンド」のイメージを持つ方もいるのではないでしょうか。
こうしたイメージの原因には、過去の一部ファンドが上場企業に対して敵対的買収を行い、人員削減による収益化や事業転売を短期的に図った例が挙げられます。
しかし、近年のファンドは「ハゲタカ」といったイメージを売手に持たれないために、企業の持続的な成長を目指す方針を明確に打ち出すケースが増えてきました。
投資ファンドは企業の成長を支えるビジネスパートナーとして機能し、売却後も従業員の給与や福利厚生の維持、企業文化の尊重を重視しています。
また、M&Aによる売却は、ビジネスや業界知識・財務知識・労務管理などの幅広いスキルが求められる複雑なプロセスとなります。
特に、投資ファンドが関与する場合は、M&Aの全プロセスをリードする中で、売却対象企業の状況や業界動向を見極め、戦略的に判断を下さなくてはならないため、投資ファンドでM&Aの最前線に立つ人材は非常に優秀なプロフェッショナルが多いと言えます。
歯科医院のM&Aでも上記同様に、医院経営の共同パートナーとして共に歩むケースが見られるようになってきました。
特に医療法人などの非上場企業の場合、そもそも外部からの乗っ取りは難しく、ファンドの役割は中長期的な支援と経営の安定化に重点が置かれる傾向です。
ファンドによっては買収後少なくとも5~10年は共同経営を行い、ファンドからも人材を派遣して経営に携わる体制を取って、じっくりと成長を支える場合もあります。
投資ファンドは企業の長期的な成長と経営の安定を重視する姿勢をアピールし、「ハゲタカ」のイメージから脱却しようとしています。
投資ファンドは売手・買手の両者が共に発展することを目的とした経営パートナーであると捉えることも、M&Aのお相手探しにおいては大切といえるかもしれません。
売却(譲渡)前と売却(譲渡)後の働き方
売却(譲渡)前の働き方
先ほどの医療法人の院長の売却前の働き方を見てみましょう。
売却前の院長は、主に週5日の勤務体制で現場に出て、週2日の休みを設けていました。
具体的には、週4日は臨床業務に従事し、残りの1日は事務日という状況です。
週5日の勤務体制はクリニックの運営において一種の安定感を持たせるものであり、経営者としての責任を果たす姿勢が見て取れます。
また、院長はクリニックの拡大を目指していたものの、法人内に相談できるパートナーがいないことが足かせとなり、自己の能力だけでは進捗が思うようにいかないことに悩んでいました。
人材育成や後継者の確保を行い組織全体の力を高めるために、信頼できる仲間との連携が必要であると認識していました。
売却(譲渡)後の働き方
売却によって、院長は買手側のグループに参画し、自身のクリニック以外のクリニック運営や買手としてM&Aにも関わることで、グループの拡大に寄与できる働き方を実現しました。
出勤スケジュールには大きな変化はなく、週3日の臨床勤務と週2日の経営業務を続けています。
売却前よりも経営業務の割合が増加した点が変わりましたが、引退ではなく事業の維持と拡大を目指す売却だったことが要因です。
新しいクリニックの開設や他の医療機関の売却を進めて大規模な歯科グループの構築を目指すために、経営業務の割合を増やした結果と言えます。
かつては売手側だった院長は、現在は買手側に立って事業戦略の策定や運営管理に関与し、規模拡大に精力的です。
投資ファンド側だけでは不足がちな、歯科医院ならではの業務や経営に関する知識を売却した院長が補うといった、良い関係性を築いています。
例えば、歯科医院経営のノウハウがある院長が、今後、買収候補となるクリニックの運営状況の評価や、強み・改善点の分析し、投資ファンドは労務や法務、財務面のチェックを重点的に行うといった役割分担です。
こうした役割分担が功を奏し、実際に、買手側の歯科グループの規模は拡大しています。
今後も、成長を目指す姿勢を維持しつつ、院長の専門的な知識や経験を活かして、より大きな歯科グループの形成が期待できるでしょう。
本事例の院長にとって、売却は単なる事業の譲渡ではなく、次なるステージへの第一歩となりました。新たな挑戦を楽しんでいる様子も伺えます。
このように、売却後も院長がクリニック運営に直接関わり、経営者としての視点強化と、さらなる成長を目指していることは、医院の拡大のみならず、院長の人生に新たなステージをもたらしたという点でも、非常に意義深いことではないでしょうか。
歯科医院ならでは!?M&A後の従業員の働き方
M&A後の従業員の働き方について、本事例の歯科医院では非常に好ましい状況が見られました。
そもそも、M&Aを決意した院長の動機の一つは、「従業員やその家族の暮らしを守ること」でした。
売却後、従業員の給料が減ったり雇用が不安定になったりすることは、必ず避けたかった事態であるため、従業員の働き方が変わらないようにM&Aを進めました。
例えば、M&Aに伴い現場のオペレーションに混乱が生じることを避けるため、現在の医院のあり方を尊重してくれるお相手を選び、自身が引き続き現場監督を行うことで、従業員にとっては従来通りの業務が継続しています。
実際、従業員の中にはM&Aが行われたこと自体を知らない方もおり、彼らの日常生活や業務に直接影響を与えるような変更がなかったことを示しています。
売主の条件は勿論ですが、同じくらい大事なこととして、M&A前後で従業員や患者さんがこれまで通り仕事や診察に来られることもあげられるのではないでしょうか。
実際に、業務に慣れ親しんだ環境の中で仕事を続けられることが、従業員のモチベーションやパフォーマンスの維持によい効果を与え、医院全体のスムーズな運営にもつながっています。
まとめ
代表水谷との売却(M&A)後の関わり方
歯科業界特化型のM&Aを手がける弊社では医院売却後も、売主の歯科医師とのお付き合いが続く場合がほとんどです。
M&Aの仲介サービス自体は、資金の支払いと経営権の移管(クロージング)をもってサービスは終了となります。
しかし、本当にいい取引が行われたかどうかは、M&A後の医院や院長、買手側の法人と長くお付き合いをして分かるものです。
売却した後でも「また水谷と食事をしたい。」「売却を考えている歯科医師に、日本歯科医療投資を紹介したい。」と思っていただけるようなM&A実績を積み重ねることで、歯科業界にさらに貢献していければと考えています。
40代(若い)年齢で歯科医院の売却を検討する方へ
40~50代という若い段階での歯科医院の売却は、人生を豊かにする大きな機会です。
事業が順調なうちに売却すると、より高額な譲渡対価となる可能性も高く、人生をより豊かにできるのではないでしょうか。
多くの売却経験者が語るように、若いうちに数億円の現金を手にすると、人生において安心感が得られ、将来の選択肢が大きく変わるともいわれています。
例えば、大きな資産を持つタイミングを80歳と40歳とで比較すると、人生における展望は全く異なるはずです。
知力と体力を活かしながら、上記を叶える手段の一つとして、M&Aによる医院売却を検討してみてはいかがでしょうか。
患者さんにもメリットが
歯科医療業界の再編が進む中、M&Aによる歯科医院のグループ化は患者さんにとっても多くの利点が期待されます。
まず、資金力のある組織がデジタル化や先進的な医療機器を導入することで、治療の質が向上します。
例えば、コミュニケーションツールやデジタルスキャンの機械を導入した歯科医院では、より正確な診断や治療計画の立案・共有が可能です。
患者さんは短時間で高精度な治療を受けられ、治療による負担も軽減されるでしょう。
また、規模の大きい医院では統一された教育基準や衛生管理が求められます。
医療の質が一層高まると共に、清潔な環境が確保されることで、患者さんは安心して治療を受けられます。
さらに、国の政策でも規模感のある歯科医院を優遇するものが示されており、1.5次歯科医療機関とも呼ばれる大きな歯科医院には診療報酬が加算され、優遇される体制が取られていります。
今後一定以上の規模を持つ歯科医院が増えることで、患者さんは質の高い医療を安定的に受けられるでしょう。
最終的には、これらの取り組みが患者さんのメリットになるだけでなく、医療従事者にとっても働きがいのある環境を提供し、全体的な医療サービスの向上へと繋がるはずです。
新たな医療環境が整備されることで、患者さんと医療者の双方にとってよい循環が生まれ、持続可能な歯科医療が実現するでしょう。